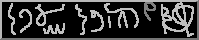
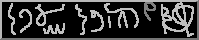
*ミトティン [#j981714b] CENTER:&size(25){Mithotyn, Mitothin, Mithothyn &br;}; 地域・文化:デンマーク ---- サクソ・グラマティクスのデンマーク歴史書『デーン人の事績(ゲスタ・ダノールム)』(13世紀初頭)第一書第7章に登場する魔法使い。死後も害悪をまきちらした。~ この部分は『ハディングスのサガ』と呼ばれる物語だが、その中にミトティンと王オティヌスの物語が、一見何の脈絡もなく挿入されている。 ハディングスが活躍していたころ、ビザンティンの王にオティヌス(北欧神話の神オージンに対応する)という人間がいた。彼は好んで北欧のウプサラに滞在し、ヨーロッパ中で自らを「神々の王」と呼ばせていた(サクソはキリスト教徒であったので、これを「偽りの」としている)。北国の王たちはオティヌスにさらなる敬意を表するため、金でこの「神」の像をつくり、ビザンティンに贈った。そして彼らは像の両腕に重い腕輪をつけた。~ オティヌスはこの贈り物を大変喜んだが、彼の妻フリッガ(これも神話中のフリッグに対応する)はその像の金を使って美しい装飾品を作ろうと思い、鍛冶屋に金を奪わせた。オティヌスは鍛冶屋をつるし首にして像を元の台座に戻した。さらに、魔法によって、像に、触れるものがあれば口を利く能力を与えた。しかしフリッガは諦めず、今度は召使の1人に身体まで与え、金を再び奪わせた。~ オティヌスは自らの像に対する不敬、それに夫婦の床に対する反逆という2つの恥辱に傷つき、流浪の旅に出ることを決めた。~ オティヌスがいなくなり王座が空になったとき現われたのが魔法使いのミトティンである。ミトティンはその魔法によって有名で、彼はそれを天からの授かりものだ、と人々に思わせていた。~ ミトティンは彼ら「野蛮なものたち」を魔法で信じ込ませ、自分を崇拝する儀式を執り行わせた。また、彼は、神々をまとめて祭祀しても怒りを静めることはできない、個別に崇拝して別々に奉納しなければならない、と定めた。さらに、魔術師の集団も組織し、神々の称号を授けた。~ しかし偉大なるオティヌスが帰還すると、ミトティンは魔法に頼るのを止めてフェオニー(フューン島)に逃げることにした。しかしそこで住人たちが彼に襲いかかり、殺してしまった。~ ミトティンは墓に埋葬されたが、死後もその魔力は継続したままだった。彼は、墓に近づくものを誰でも殺してしまったのである。島の住人たちは困ってしまったので、遺体を塚から引きずり出して、頭を切り落とし、胸に杭を打ち込んだ。こうしてやっと、島の人々はミトティンの魔力から解放された。~ オティヌスのほうはというと、彼は玉座に戻ると、ミトティンの配下の魔術師たちを全て追放したのであった(妻は死んでいたらしい)。 この物語については、古くから北欧神話におけるアース神族とヴァン神族の対立と融和のモティーフが歴史的な物語になったのだと言われてきた。その詳細は専門書に譲るとして、ではミトティンは何かというと、ジョルジュ・デュメジルの『神話から物語へ』によると、オティヌス=オージンのアース神族に対立するのだからヴァン神族であるということになる。神話では2つの神族は融和するが、『デーン人の事績』ではミトティンは完全に敗れる。さらに、神話(『ユングリンガ・サガ』、『詩語法』)ではクヴァーシルというヴァン側の神がアース神族に渡され、彼は世界中を回って人々に知恵を授けるが、2人の小人に殺されてしまう。その血は蜂蜜と混ぜられ、オージンの蜂蜜酒ミョズとなる。このクヴァーシルが、異国を彷徨っていて殺されるミトティンに対応すると言われる。クヴァーシルとミトティンの名前は似ていないが、デュメジルはミトティンの綴りがMith-ot(h)ynに分解できることを指摘した。上にあるように『デーン人の事績』ではオージンはオティヌス(Othinus, Othynus)と表記され、ときにオティン(Othin)となる。「オージンのミョズ」は「Óðinnのmjöðr」であり、それが「othinのmith」になったというのがデュメジルの説である。 **関連項目 [#rb885ac6] -[[東欧/ヴァンパイア]] -[[キーワード/魔術師]] ---- 参考資料 - [[資料/151]]: